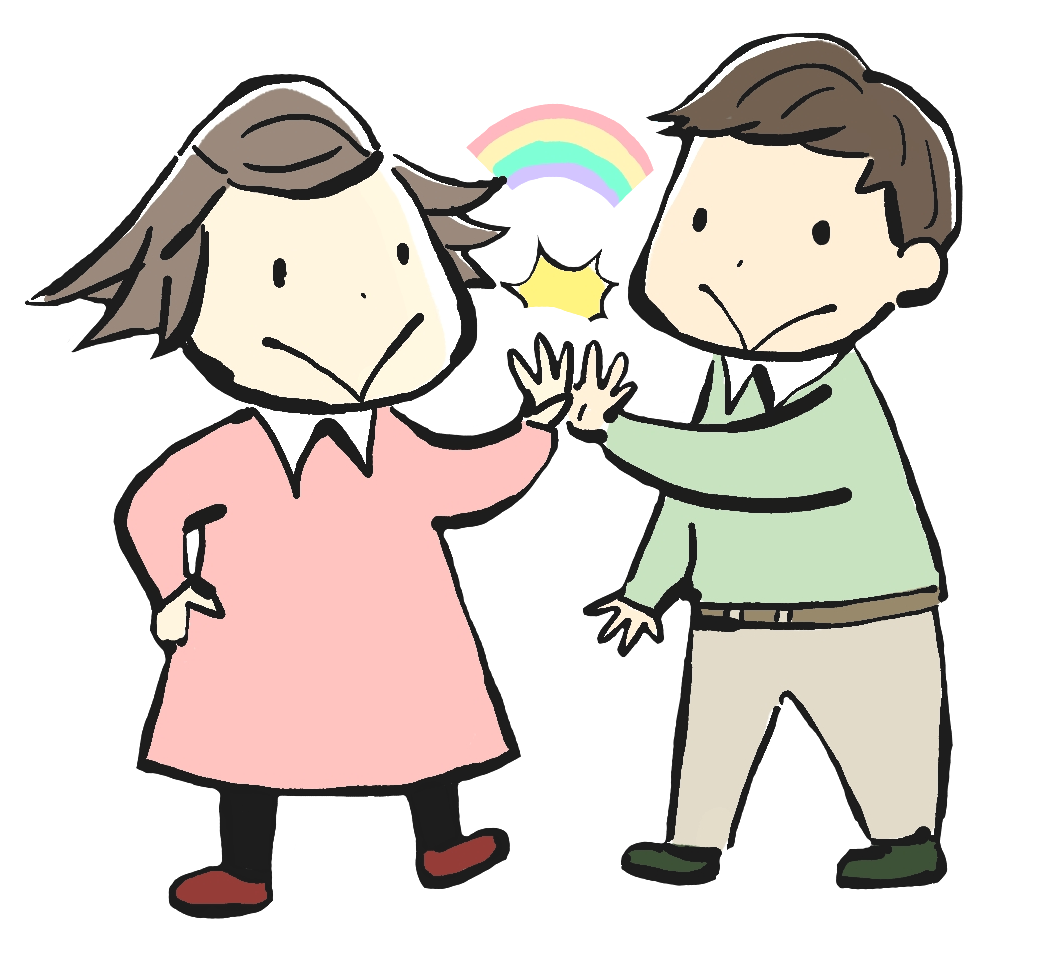 このコロナ禍、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
このコロナ禍、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
快適な”ステイホーム”期間を過ごした方もいる一方で、トップページにも書いたとおり、家庭の中で辛い思いをしている(特に)女性や子どもたちがきっとたくさんいるのだろうと、いつも心のどこかに引っかかっています。
今年4月、立憲民主党がDV防止法改正に向けた提言を発表しました。
https://cdp-japan.jp/news/20200427_2881
DV防止法はほんとうにいろいろ足りないところだらけで、大改正の必要性がずっと指摘されているのに、国会の動きはほんとうに鈍いものです。
そんななかで、立憲民主党がまっさきにこれに真正面から取り組んだということ、(同党にはいろいろ言いたいことはありますが)率直に評価しています。
ただやはり、現場で日々、はいつくばるようにして働く私たちのような立場からすると、気になる点がいくつかあります。
そのうち2点に絞ってなんとかがんばって意見書にまとめて、尊敬する先輩弁護士でもある打越さく良参議院議員に託しました。
ここに、全文を引用します。
長いですが、ご関心のある方はぜひご一読ください。
o゜○・o。O.゜。o・。o○・o。o゜○・o。O.゜。o・。o○・o。
私は、大阪弁護士会に所属する弁護士です。
御党が今年4月2日付で発表した標題の提言(以下、「本提言」といいます)は、保護命令の対象となる「暴力」を定義規定のそれと一致させることや、被害者の迅速な救済を可能とする手続を整備することをはじめ、これまでの法の不備や不十分な点を的確にカバーする内容を含むものであり、この間のご努力に敬意と感謝をまずはお伝えいたします。
そのうえで、私が弁護士として夫婦・親子の紛争を扱った経験などを踏まえ、以下の2点に絞って、意見を申し上げます。
1,面会交流を禁止・制限することの位置づけ
面会交流について、本提言においては「子どもの保護」のための施策と(のみ)位置づけられているように理解されます。
もとより、面会交流の場において、子どもが直接に有形無形の暴力を受けたり、それを目撃させられたりすることから、子どもを守るべきことはいわずもがなです。
しかし、およそDV事案における面会交流は、それ自体が、加害者による被害者(監護親)に対する支配や攻撃・嫌がらせの格好の手段です。加害者がこれを要求する意図はまさにその点にあるとすらいえると私は思っています。
私の経験においても、加害者が、面会交流に被害者(監護親)が同行しなければ養育費を渡さないと脅したうえ、面会交流の場では子どもたちだけで遊ばせておいて、その陰で性暴力(表面的には「合意」のうえの性的行為)に繰り返し及んだという事例すらありました。
これは最もひどい例でしたが、多くのケースで、たとえば加害者の面会交流の要求に対して被害者が少しでも異議や意見、どころか日程変更の打診すらも、言葉にするだけで、全人格を否定するような言葉で罵倒したり、親権を奪うぞと脅したり、直前の面会実施・予定変更・中止の要求(強要・脅迫)を繰り返して監護親と子どもたちを振り回す(結果的に監護親と子どもたちは週末等の予定を全く立てられなくなる)といったように、加害者を相手とする面会交流は、その事前の協議や日程調整も含めて、被害者である監護親にとって、過酷ともいうべき負担になりうるものです。
このように、加害者は、面会交流の機会(あるいは子ども)を利用して、その支配下から逃れようとする被害者(監護親)に対して、支配の継続あるいは報復、嫌がらせを行い(または行おうとし)ます。これは私の感覚だけであえて申し上げれば、すくなくとも男性加害者についてはほぼ例外ありません。
他方で、家庭裁判所の実務においては、面会交流の意義を過度に評価(ありていにいえば不必要に美化)し、「夫婦と親子の問題は別」「子どもに対して直接的な暴力や暴言がなければ実施すべき」「面前DVの心配がある場合には第三者などの援助を得ればよい」といった意識がまだまだ根強くあります。面会交流を促進したいあまりに、DV加害ということの本質を意図的に無視ないし軽視、あるいは矮小化している、というのが偽らざる実感です。それがために、加害者の真の意図が見過ごされ、面会交流の実施が陰に陽に強要され、多くの被害者(監護親)が、ときには同居中と大差ないほどに、苦しく辛い状況に追い込まれています。
したがって、法律を整備するにあたり、DV事案における面会交流制限は、端的に、監護親である被害者の保護と(も)位置づけることが肝要であると考えます。
2,加害者プログラムの位置づけ
① 同居継続・再開に向けた支援と位置づけるべきでないこと
本提言中、加害者プログラムの必要性については、「内閣府の調査によれば、加害配偶者と別れた被害者は約1割であり、同居を続けたまま、加害行為がなくなることを願う被害者がいる等の現状を踏まえ」たものと明記されています。
加害者の更生のための施策を、同居の継続を望む被害者の支援ないし救済のための施策と位置づける趣旨と理解されますが、この位置づけは、ぜひご再考いただきたいと思います。「加害者更生プログラム」が目指すべき目標地点をくれぐれも見誤らないよう、丁寧に検討してください(後記③)。
いうまでもなく、被害者が加害者との同居の継続(ないし回復)を臨む最大の理由は、多くの場合、加害者が生計の主たる担い手である(それはまた、加害者による経済的・社会的支配の結果である蓋然性がきわめて高い)ことによる、離別に伴う経済的な不安です。
これに加えて、被害者に特有の責任感や罪悪感、子どもから一方の親を奪うことへの躊躇といった、さまざまな負の感情(社会的な刷り込み)も大きいでしょう。
こうしたものを全て完全に排除してなお、加害者との同居の継続・回復を望む被害者が、果たしてどれだけいるでしょうか。
それでなくても被害者は、日々繰り返された有形無形の理不尽な虐待によって、心に深い傷を負い、また怒りや屈辱感といった負の感情をため込んでいます。たとえ加害者が「更生」したとしても、その人と同居を継続・回復すれば、こうした感情の健全な処理を困難にし、ダメージからの回復のプロセスを阻害しかねないと、私は思います。
DV防止法のおおもとの理念・目的に照らせば、およそ被害者支援のための特定の制度について、同居の継続・回復を後押しするかのような位置づけをすることは、被害者に対する上記社会的な刷り込みを強化し、心の傷の修復をも困難にしかねず、慎重であるべきです。
他方で、加害者更生ということの本来的な困難さ(後記②)は、すでに多くの取り組みの中でも明らかになっています。
以上のことからすれば、被害者が加害者との同居の継続(回復)を望む場合にこそ肝要であるのは、何を措いてもまずは経済的支援あるいは経済的自立の促進と、精神的サポート、つまり、加害者更生がきわめて困難であることの正しい理解を促す働きかけと、被害者が加害者や子に対して感じる(いわれのない)罪悪感などの負の感情を取り除く働きかけです。この優先順位のつけかたを、いささかなりとも誤ってはいけないと思います。
② 加害者の更生がほぼ望めないこと
本提言の策定にあたっては、すでに加害者支援に取り組む方々からの意見や助言を得ていることと思いますが、加害者プログラムは、各国に先んじてこれに取り組んでいるアメリカなど諸外国の実践すらも、まだ努力の途上にあって、その成果あるいは効果はきわめて限定的といわれています。それどころか、その深刻な”副作用”として、加害者がより巧妙な支配の手口を学び取り、その人格の偏りや認知の歪みを増長する危険性すら指摘されているところで、こうした点からも、立法に際しては、その制度設計も含め、きわめて慎重である必要があります。
ここにおいては、加害者の思考・行動パターンを変えることそれ自体が、ほぼ不可能というべきほどに困難であるということを、逃げることなく直視すべきです。
加害者がそのパートナーを支配下に置き、有形無形の暴力によって恐怖させ思い通りに操るという行動パターンの基盤には、加害者特有の歪んだ思考パターンがあります。その最大公約数的な要素は、自分には被害者を支配し隷従させることが当然に許されていて、被害者が自分に逆らえばそれに対していかなる制裁をも加えることは、自分に当然に許された正当な行為であるというような、歪んだ特権意識ともいうべきものです。加害者は、このような考え方を身に染みつけています。
いうまでもなくこれは、一朝一夕に身につくものではなく、多くは、幼少期から、その親など近しい大人の言動から学び取るなどし、なおかつ成長過程においてそれを学び落とすこともないままに、大人になってしまった結果です。
もともと、成長過程で身につけた思考・行動パターンの誤りを認めてこれを改めるということは、何人にとっても容易ではありません。いわんや加害者が身に染みつけた思考パターンは、自分を特権的地位と正当性を信じて疑わず、不都合なことはすべて他者に転嫁するというものです。
加えてそれは、加害者に「うまみ」をもたらします。パートナーを支配し思い通りに操ることで、加害者は、物的サービスはもちろん、「常にいい気分でいさせる」という感情的サービスから性的サービスまで、あらゆる奉仕を受けることができます。
これはある種の依存ともいえますが、たとえばこれがギャンブルやアルコールの場合なら、本人自身がそれによってなんらか身を削り、いずれ経済的破綻や大病などのかたちで、「懲りて立ち直る」ための大きな契機となりうる事態(心理の領域でいうところの「底つき体験」)に至ります。
しかし、DVの加害者がこのような事態に至ることは、まずありません。被害者による離別というのはひとつの「底つき体験」類似の状況とはいえますが、それ自体は加害者にとって致命的な痛手とはなりえず、代わりの依存(支配)対象を得ることで、「底つき」の状態を回避することができます。
このように、加害者の思考・行動パターンを変えること自体が困難であるうえ、その動機付けにも乏しいという意味でも、加害者の「更生」とは、本来的に、ほとんど期待することができないものです。
加害者の更生について何らかの立法的措置が必要であるとしても、その位置づけ(上記①に述べたところの優先順位)が、正しく検討されなければなりません。
③ 加害者プログラムの目指すべきところ
加害者プログラムの根本的な問題として、そもそも何を目標とすべきか、なにをもって「更生」したと評価ないし認定をするのか、そしてそれを誰がすべきか、という問題は、本提言の策定において、いかに検討されたのでしょうか。
「同居を続けたまま、加害行為がなくなることを願う被害者」の存在が主要な立法事実と位置づけられていると読めることから、そこから自然に理解されるところは、すくなくとも目標は、被害者との平穏な夫婦共同生活の実現ないし再開であり、それができる程度に加害者が自身の感情や言動をコントロールできるようになること(そのようにプログラムの実施者?被害者?が判断した状態)が「更生」と位置づけられるのでしょうか。
しかし、加害者プログラムが必然的に抱える上記”副作用”のリスク、そして被害者自身が深く傷ついており、立ち直りの途上にあることが普通でしょうから、そもそもその評価ないし認定自体(と、同居を継続・回復するという意思決定)が、冷静妥当にされうるのか、情にほだされたり加害者にだまされたりする危険性をどう排除するのか、という問題がまずあります。「更生」したようだから同居を再開してみましょう、それでもしもまだ「更生」できていなかったらまた逃げなさい、ということでは、被害者はいつまでも加害者に振り回され続け、傷つけられ続け、その人生の立て直しを大きく阻害される(先送りや遠回りをさせられる)のですから、そんな無責任な話はありません。
仮に同居の回復が将来ありうるとしても、それは、上記①の最後に指摘したとおり、被害者自身が適切なサポートを受けて精神的なダメージから回復し、経済的にも加害者に依存しなくても生活できるようになって、真に自由な意思決定ができる状態になってからのことでなければなりません。法は、被害者の真に自由な意思決定をこそ、支え後押しするものであるべきです。
この観点から、およそ加害者プログラムにおいて「更生」と評価ないし認定される状態は、加害者が、被害者との離別を受け入れ、依存や執着を完全に捨て去ること、そして他者との間で、対等で平穏なパートナーシップを築けるようになること、ということができます。
これを被害者の立場から言えば、加害者の陰におびえることなく、安心して、安全に生活することができることです。
加害者更生プログラムについての立法は、必ずそのような方向性を指向するものでなければならないと思います。
(以上)
